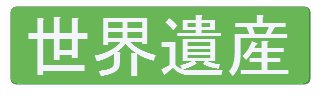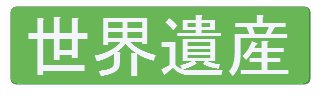琉球の歴史概要
琉球の歴史概要
琉球は、1000年以上前から国家らしきものがあったようで
すが定かではありません。歴史上の最初の王は1187年に即位した舜天(しゅんてん)王という人物
で、琉球に逃れた源為朝の子孫との伝説もありますが、これも定かではありません。次に現われたのが1260年に即位した英祖(えいそ)王で、実際に浦添
城の「浦添ようどれ」と呼ばれる墓が存在します。次は1350年即位の察度(さっと)王で、初めて中国
明朝と貿易を行った人物です。このあたりから歴史は伝説から史実へと移ってゆきます。
これらはそれぞれ数十年、複数代にわたって存続した王統ですが、いずれも浦添近辺を拠点とした一地方の勢力だったと考えられます。この時代はまだ中央集
権国家なるものは存在していませんでした。
察度王の時代以前から、各地方では豪族が勢力拡大を繰り返して台頭し、やがてそれらは三つの勢力に収斂(しゅうれん)されてゆきます。北部では本部半島の
今帰仁城を拠点とする勢力、中部は浦添城(首里城の説もある)の察度王統の勢力、南部では南山城(現在の糸満市)を拠点とする勢力、これら三つの勢力を、
それぞれ北山(ほくざん)、中山(ちゅうざん)、南山(なんざん)とよび、この時代を三山(さんざん)時代とよびます。いわゆる日本の戦国時代にあたりま
す。
この戦国時代を終わらせたのが南東部の佐敷(現在の佐敷村)から中央へと進出し、1406年に察度王統を滅ぼして中山のニューリーダーと
なった尚巴志(しょう・はし)でした。尚巴志は1416年に北山を攻略し、1429年ついには南山を滅ぼして琉球統一を成し遂げました。
七代続
いた尚巴志の王統でしたが、1469年に終焉を迎えます。王国内のクーデターで王の一族は滅ぼされ、代わって尚円(しょう・えん)が王位につきます。尚の
名が同じなのは中国との貿易外交上の都合で、実際は新しい王統の誕生でした。尚巴志の王統を第一尚氏、尚円の王統を第二尚氏とよびます。
尚円王統時代に琉球は全盛期を迎えます。中国との貿易で国が栄え、戦争のない平和な時代が続きました。しかし、1609年薩摩藩の侵略であっけなく首里
城は陥落してしまいます。長い平和な時代が、琉球の戦う力を失わせてしまっていたという皮肉な結末でした。
中国貿易の利権をねらった薩摩は表向き琉球王国を存続させましたが、この時点で独立国としての琉球の歴史は終わりました。名実ともに琉球が歴史から消え
たのは明治維新の廃藩置県の時で、以後琉球は沖縄になりました。
【琉球歴史年表】
年代出来事
1187舜天王即位
1260英祖王即位
1314〜このころ三山対立が始まる
1350察度王即位
1402尚巴志が島添大里按司を滅ぼす
1406尚巴志が察度王統を滅ぼし、父の尚思紹が中山王となる
1416中山が北山を滅ぼす
1422尚巴志が中山王に即位する
1429中山が南山を滅ぼし三山を統一する
1440尚忠(尚巴志次男)即位
1445尚思達(尚忠長男)即位
1450尚金福(尚巴志五男)即位
1453志魯・布里の乱
1454尚泰久(尚巴志七男)即位
1458護佐丸・阿麻和利の乱
1461尚徳(尚泰久三男)即位
1470尚円が琉球王に即位し、第二尚王統が始まる
1477尚宣威(尚円弟)即位
1477尚真(尚円長男)即位
1492円覚寺建立
1501玉陵築造
1502円鑑池・弁財天堂築造
1527尚清(尚真五男)即位
1556尚元(尚清次男)即位
1573尚永(尚元次男)即位
1589尚寧即位
1609薩摩藩による琉球侵略
1872琉球藩となる
1879琉球処分、沖縄県となる